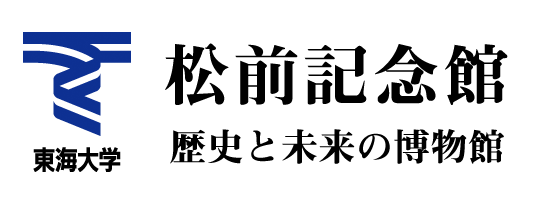ホーム > 当館について > 松前記念館 概要
≡ 松前記念館 概要
館長挨拶
松前記念館(東海大学 歴史と未来の博物館)は、東海大学の建学40周年記念事業の一環として1983年の建学記念日に開館しました。学園の創立者・松前重義の思想と業績を後世に伝えるとともに、東海大学の建学の理念を継承し、学園が理想とする教育研究に資することにより、広く社会に貢献することを目的としています。その核心は「科学技術は人類の幸福のためにあるものである。しかし、その取り扱いを間違うと人類を破滅へと導く。国の行方も人類の将来もこれに関わる人間の思想に左右される」という松前自身の言葉に表れています。
それからさらに40年、2022年には建学80周年を迎えました。大きく変化する世界において、本学が掲げる理念とそれに基づく教育・研究活動は、ますます重要な使命を帯びてきました。東海大学の歩んできた歴史と、そこで「文明」「文理融合」の眼差しとともに育んできた「知」の集積を、しっかりと次世代へ継承し、地域や国際社会とともに未来を創造していく、新たなミュージアムを目指しています。
松前記念館は2025年度からは館の運営を学長室が引き継ぎ、「学問分野の際を越え」「ともに学び」「その成果をデジタル資産として残していく」目標をひきつづき掲げ-図書館や学園史資料センターとも連携し、まさに館の愛称である「歴史と未来の博物館」の実現に邁進します。どうか、ご期待ください。
それからさらに40年、2022年には建学80周年を迎えました。大きく変化する世界において、本学が掲げる理念とそれに基づく教育・研究活動は、ますます重要な使命を帯びてきました。東海大学の歩んできた歴史と、そこで「文明」「文理融合」の眼差しとともに育んできた「知」の集積を、しっかりと次世代へ継承し、地域や国際社会とともに未来を創造していく、新たなミュージアムを目指しています。
松前記念館は2025年度からは館の運営を学長室が引き継ぎ、「学問分野の際を越え」「ともに学び」「その成果をデジタル資産として残していく」目標をひきつづき掲げ-図書館や学園史資料センターとも連携し、まさに館の愛称である「歴史と未来の博物館」の実現に邁進します。どうか、ご期待ください。

松前記念館 館長 水島 久光
| 館長 | 水島久光 | 文化社会学部・教授 / 学長室(MLA担当)部長 |
|---|---|---|
| 学芸/事務 | 篠原聰 | 資格教育センター・准教授 / 学長室(松前記念館担当)課長 / 学芸員 |
| 学芸/事務 | 田中実紀 | 学長室(松前記念館担当)/ 学芸員 |
| 事務 | 森真理子 | 学長室(松前記念館担当)/ 事務職員 |
1983年(昭和58)年の開館当時、1階展示室には松前重義の世界的発明として知られる無装荷ケーブルおよび同搬送装置や、1944年(昭和19)の東海道1号同軸ケーブル、日満無装荷ケーブル、吉見―岩国間、小山―宇都宮間、尾道―美ノ郷間の各無装荷ケーブル敷設当時の写真資料のほか、松前が『電信電話学会雑誌』に発表した論文、無装荷ケーブル通信方式による世界通信網の構想図や、学園創立基金の寄付者銘板(コピー)などが展示されました。展示資料には無装荷ケーブル通信方式の開発に携わった企業や電電公社(現・NTT)から提供された貴重な近代化遺産資料なども含まれます。2階展示室には「聖書研究会」、望星学塾、英世学園など、大学前史からの資料・文献・写真・パネルをはじめ松前の著書・原稿・蔵書、学園創設期の関係者の資料などが展示され、学園の歩みをたどることができる内容でした。 他方、個人を顕彰する記念館として開館した経緯もあり、開館後は展示の更新などは行われず、パネル類も次第に色あせてきました。
2004年(平成16)、館長に松前紀男(当時・東海大学副理事長)が就任、「学内のみならず広く学外にも開かれた博物館、語りかける、行動する博物館(当時の館長挨拶より)」を目指し、建学の歴史や各学部学科創設の理念等に関する幅広い企画展を開催する方針が示され、難波克彰事務室長を中心に年2回の企画展を開催し、2010年(平成22)からは常設展と企画展のマイナーチェンジやミニ企画展の開催など、年に数回展示を更新しています。
2015年(平成27)に橋本敏明が館長に就任してからは、学園史資料センターをはじめとする学内関連部署との連携を深め、大学コレクションの活用を図るなど、大学博物館としての役割や機能を強化するとともに、年齢や性別、国籍、障害の有無にかかわらず誰もが楽しめる博物館の実現を目指すユニバーサル・ミュージアムの実践にも力を入れてきました。
2023年(令和5)に水島久光(文化社会学部広報メディア学科教授)が館長に就任。博物館・図書館・学園史資料センターとの連携(MLA連携)を強化するとともに、古代エジプトやアンデスなどの大学コレクションを活用した文理融合による特別展の開催などをスタートさせ、博物館のリニューアルを進め、MLA連携によるデジタルを活用したミュージアムの実践にも力を入れています。
松前記念館の使命(ミッション)
松前記念館の沿革
1983年(昭和58)
松前記念館開館、初代館長に松前達郎が就任
1998年(平成10)
東海大学松前記念館と改称(館長:松前達郎)
2003年(平成15)
館長に難波克彰が就任
2004年(平成16)
リニューアルオープン
館長に松前紀男が就任
神奈川県から博物館相当施設の指定を受ける
博物館実習の受け入れ開始
館長に松前紀男が就任
神奈川県から博物館相当施設の指定を受ける
博物館実習の受け入れ開始
2009年(平成21)
開館25周年記念講演会(デンマーク関連)
「東海大学の教育の源流―世界一幸せな国をつくった教育―」
「東海大学の教育の源流―世界一幸せな国をつくった教育―」
2010年(平成22)
館長に松前達郎が就任
講堂にて「アインシュタインLOVE in 東海大学」展
講堂にて「アインシュタインLOVE in 東海大学」展
2014年(平成26)
館長に山田清志が就任
2015年(平成27)
館長に橋本敏明が就任
2016年(平成28)
文化財保存修復学会第38回大会を開催
2017年(平成29)
建学75周年記念事業(講演会)
世界一幸せな国をつくったデンマークの国民高等学校」
世界一幸せな国をつくったデンマークの国民高等学校」
2018年(平成30)
エントランスロビーにて「世界のたね」展
2020年(令和2年)
エントランスロビーにて「手の世界制作」展
2021年(令和3年)
エントランスロビーにて「水、呼吸、命のかたち(手の世界制作-2)」展
2022年(令和4年)
文理融合による特別展「古代アンデスの音とカタチ」展
エントランスロビーにて「かたちの生命(手の世界制作-3)」展
エントランスロビーにて「かたちの生命(手の世界制作-3)」展
2023年(令和5年)
館長に水島久光が就任
文理融合による特別展「古代エジプト 受け継がれる祈りの心」展
エントランスロビーにて「インナービジョンズ(手の世界制作-4)」展
文理融合による特別展「古代エジプト 受け継がれる祈りの心」展
エントランスロビーにて「インナービジョンズ(手の世界制作-4)」展
2024年(令和6年)
MLA連携による特別展「書物の地層をたどる」展
エントランスロビーにて「世界のたね」展
エントランスロビーにて「世界のたね」展
私学の特質と建学の精神
松前重義「苦難に耐えて建学の理想を貫こう」(『望星教育』第1巻, 1969)より
ここで、私どもは、私学の本質について反省してみたいと思うのであります。日本国憲法は国民に自由を与えました。思想の自由、集会、言論の自由を与えました。であるならば、学園内は自由であるべきではないか、という考え方があり得るのであります。
しかしながら、日本国憲法は、国民に自由を与えた。その与えられたる自由によって、それぞれの特徴ある教育方針によって私学は自由に建学をいたしました。自分はこういうような教育をして人造りをしたい、即ちキリスト教に基づく教育機関をつくりたい、あるいは仏教に基づく教育機関をつくりたい、あるいはまたこれこれの建学の理想をもって教育する学校をつくりたい。これらのいろいろの色とりどりの学校を、自由に、それぞれの色合いをもって私学は建学されてまいったのであります。私学の花園には赤い花があったり、黄色い花があったり、紫があったり、白があったり、桃色があったりするところに、色とりどりの自由な配合となって、国家全体として調和がとれたものとなるのであります。
赤い花を好きな者は、赤い花をつんだほうがよろしい。紫を好きな者は紫をつんだらよろしい。私学にはこのような色合いの特徴がある。私学としてある方面に特徴があるなら、その特徴を選んで入学を希望するというようなことで、それぞれみずから建学の色合いを見て、それぞれ自分の好きな花を自由につむことが出来るのであります。
その大学の入学に関する選択については完全に憲法によって保障された国民としての自由が与えられておる。けれども、その建学の目的と精神によって建設された学校に入学した者は、その建学の精神を理解し、これに基づく教育を是認しなければならないことは、当然であります。むしろ喜びをもって、そのそれぞれの建学の精神によってみずから人となる努力をしなければならないのであります。もし建学の精神が自己の思想に合致しないならば、自由に他の合致する大学を選んで入学すべきであります。
国民に与えられた自由なるものは、各々私学に与えられた自由であります。私学に与えられた自由は、それぞれの社会という花園における色合いとなって、それぞれの自由を誇るのであります。そこにいろいろとりまぜたところの色の配合によって文化の色彩があざやかに織りなされることになるのであります。
こういう意味におきまして、私学には私学としての建学の精神と理想がなければなりません。官立の場合においては、国民全体の税金で支えられているから色合いはない。無色でありますから、そこに特徴もなく無性格のものである。どちらを向いても自由である。だが私学の場合は、建学の目的がある。それぞれ違った色合いの建学の目的がある。そのそれぞれの色を好んで学生は入って来る。
こういうような意味におきまして、建学の理想に向かって邁進することこそが私学存在の意義があるのであります。もしも建学の理想が見失われ、そして、その精神と目的とが喪失されるとするならば、即ち私学が官立と同じになるとするならば、その私学の存在の意義はないと思うのであります。ただ月謝をとって、知識を教えて、それで終り。それならば何も私学をつくる必要はないのであります。学校教育法、あるいはまた教育基本法等にもられている私学に対する考え方は、まさにここにある。われわれは、このようにして、われわれの建学の精神と、その理想、その目的に向かって、ともに手を取り合って、邁進したいと思うのであります。
今日、私学として進まなければならない道は、すなわち、ただいま申し上げましたような建学の基本的な理念と、それをいかにして教育の中に生かしていくか、進めていくか、ということであります。この努力の道を皆さん方とともに進んでいきたいと思うのであります。
ここで、私どもは、私学の本質について反省してみたいと思うのであります。日本国憲法は国民に自由を与えました。思想の自由、集会、言論の自由を与えました。であるならば、学園内は自由であるべきではないか、という考え方があり得るのであります。
しかしながら、日本国憲法は、国民に自由を与えた。その与えられたる自由によって、それぞれの特徴ある教育方針によって私学は自由に建学をいたしました。自分はこういうような教育をして人造りをしたい、即ちキリスト教に基づく教育機関をつくりたい、あるいは仏教に基づく教育機関をつくりたい、あるいはまたこれこれの建学の理想をもって教育する学校をつくりたい。これらのいろいろの色とりどりの学校を、自由に、それぞれの色合いをもって私学は建学されてまいったのであります。私学の花園には赤い花があったり、黄色い花があったり、紫があったり、白があったり、桃色があったりするところに、色とりどりの自由な配合となって、国家全体として調和がとれたものとなるのであります。
赤い花を好きな者は、赤い花をつんだほうがよろしい。紫を好きな者は紫をつんだらよろしい。私学にはこのような色合いの特徴がある。私学としてある方面に特徴があるなら、その特徴を選んで入学を希望するというようなことで、それぞれみずから建学の色合いを見て、それぞれ自分の好きな花を自由につむことが出来るのであります。
その大学の入学に関する選択については完全に憲法によって保障された国民としての自由が与えられておる。けれども、その建学の目的と精神によって建設された学校に入学した者は、その建学の精神を理解し、これに基づく教育を是認しなければならないことは、当然であります。むしろ喜びをもって、そのそれぞれの建学の精神によってみずから人となる努力をしなければならないのであります。もし建学の精神が自己の思想に合致しないならば、自由に他の合致する大学を選んで入学すべきであります。
国民に与えられた自由なるものは、各々私学に与えられた自由であります。私学に与えられた自由は、それぞれの社会という花園における色合いとなって、それぞれの自由を誇るのであります。そこにいろいろとりまぜたところの色の配合によって文化の色彩があざやかに織りなされることになるのであります。
こういう意味におきまして、私学には私学としての建学の精神と理想がなければなりません。官立の場合においては、国民全体の税金で支えられているから色合いはない。無色でありますから、そこに特徴もなく無性格のものである。どちらを向いても自由である。だが私学の場合は、建学の目的がある。それぞれ違った色合いの建学の目的がある。そのそれぞれの色を好んで学生は入って来る。
こういうような意味におきまして、建学の理想に向かって邁進することこそが私学存在の意義があるのであります。もしも建学の理想が見失われ、そして、その精神と目的とが喪失されるとするならば、即ち私学が官立と同じになるとするならば、その私学の存在の意義はないと思うのであります。ただ月謝をとって、知識を教えて、それで終り。それならば何も私学をつくる必要はないのであります。学校教育法、あるいはまた教育基本法等にもられている私学に対する考え方は、まさにここにある。われわれは、このようにして、われわれの建学の精神と、その理想、その目的に向かって、ともに手を取り合って、邁進したいと思うのであります。
今日、私学として進まなければならない道は、すなわち、ただいま申し上げましたような建学の基本的な理念と、それをいかにして教育の中に生かしていくか、進めていくか、ということであります。この努力の道を皆さん方とともに進んでいきたいと思うのであります。